🌀冷え性におすすめの漢方と飲み方の工夫
〜体質に合わせた処方選択と服用管理で、冷えにくい身体づくりを〜
こんにちは。今回は、季節の変わり目や冬場に多くなる「冷え性」について、漢方医学の視点から詳しく解説します。
冷え性は単なる不快症状ではなく、血流障害・自律神経の乱れ・水分代謝異常・ホルモンバランスの崩れなど、複数の要因が絡み合う“体質的課題”です。
西洋医学では「冷え性」という診断名は存在しませんが、漢方では「寒証」「虚証」「瘀血」「水毒」などの概念を用いて、個々の冷えの背景にアプローチします。
❄️冷え性の分類と漢方的病態理解
漢方では、冷え性を以下のように分類し、それぞれに異なる治療方針を立てます。
| タイプ | 主な症状 | 漢方的病態 | 原因例 |
|---|---|---|---|
| 四肢末端型 | 手足の冷え | 気血の停滞、瘀血 | ストレス、自律神経失調、血流障害 |
| 内臓型 | 下腹部・腰の冷え | 腎陽虚、脾虚 | 胃腸虚弱、代謝低下、ホルモン不均衡 |
| 全身型 | 体全体の冷え | 気虚・血虚・陽虚 | 貧血、低血圧、甲状腺機能低下 |
💡冷え性は、全身の「気・血・水」のバランス異常として捉えることが重要です。
🌿冷え性に用いられる代表的な漢方処方
① 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
- 構成:当帰・芍薬・川芎・茯苓・白朮・沢瀉
- 作用:補血・活血・利水
- 適応:虚弱体質で冷えやすく、むくみや倦怠感を伴う女性
② 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 構成:桂皮・茯苓・牡丹皮・芍薬・桃仁
- 作用:瘀血改善・血流促進・抗炎症
- 適応:肩こり・頭痛・月経痛・下腹部の冷えを伴う瘀血体質
③ 八味地黄丸(はちみじおうがん)
- 構成:地黄・山茱萸・山薬・沢瀉・茯苓・牡丹皮・桂皮・附子
- 作用:腎陽を補い、下半身の冷え・頻尿・腰痛を改善
- 適応:加齢による冷え、夜間頻尿、足腰のだるさ
④ 真武湯(しんぶとう)
- 構成:附子・茯苓・白朮・生姜・芍薬
- 作用:脾腎陽虚による水毒を改善し、冷え・下痢・むくみを緩和
- 適応:胃腸虚弱、水分代謝異常、寒湿による冷え
※同じ冷え性でも、体質(証)により処方が異なるため、専門家の判断が重要です。
🍵服用管理と吸収効率を高める工夫
- 白湯で服用:体温を下げず、薬効成分の溶解と吸収を促進
- 食前30分が基本:胃が空の状態で吸収率が高まる
- 朝・夕の分服:冷えが強くなる時間帯に合わせて服用
- 継続服用:最低1〜2ヶ月の継続が推奨される
💡服薬記録アプリや「お茶の時間に合わせる」などの習慣化も効果的です。
🧑⚕️薬剤師からの服用指導ポイント
- 副作用:胃部不快感、下痢、発疹などが報告されることも
- 相互作用:利尿薬・降圧薬・抗凝固薬などとの併用に注意
- 妊娠・授乳中の使用:一部の生薬(桃仁・牡丹皮など)は禁忌となる場合あり
- 市販品と医療用の違い:含有量・添加物・剤形が異なるため、選定には専門的判断が必要
🧭まとめ:冷え性は“証”に基づくアプローチで改善できる
冷え性は、体質的なバランスの乱れを示す重要なサインです。漢方医学では、個々の「証」に基づいて処方を選び、服用管理を通じて体質改善を図ります。
薬剤師としては、冷えのタイプを見極め、適切な処方と服用指導を行うことで、「冷えにくい身体づくり」をサポートすることが可能です。
この秋冬は、漢方の力を借りて、根本から冷え性に向き合ってみませんか?
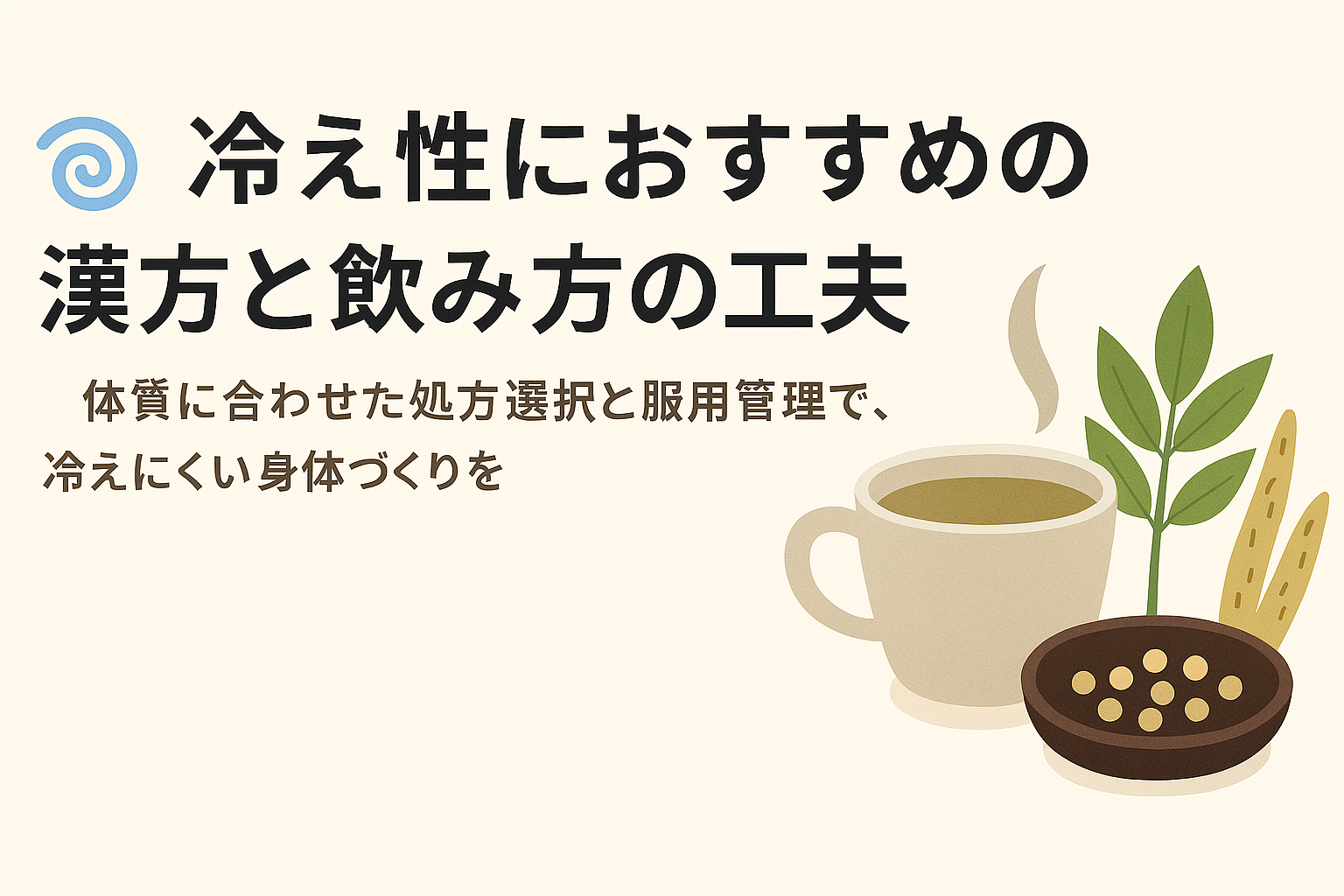
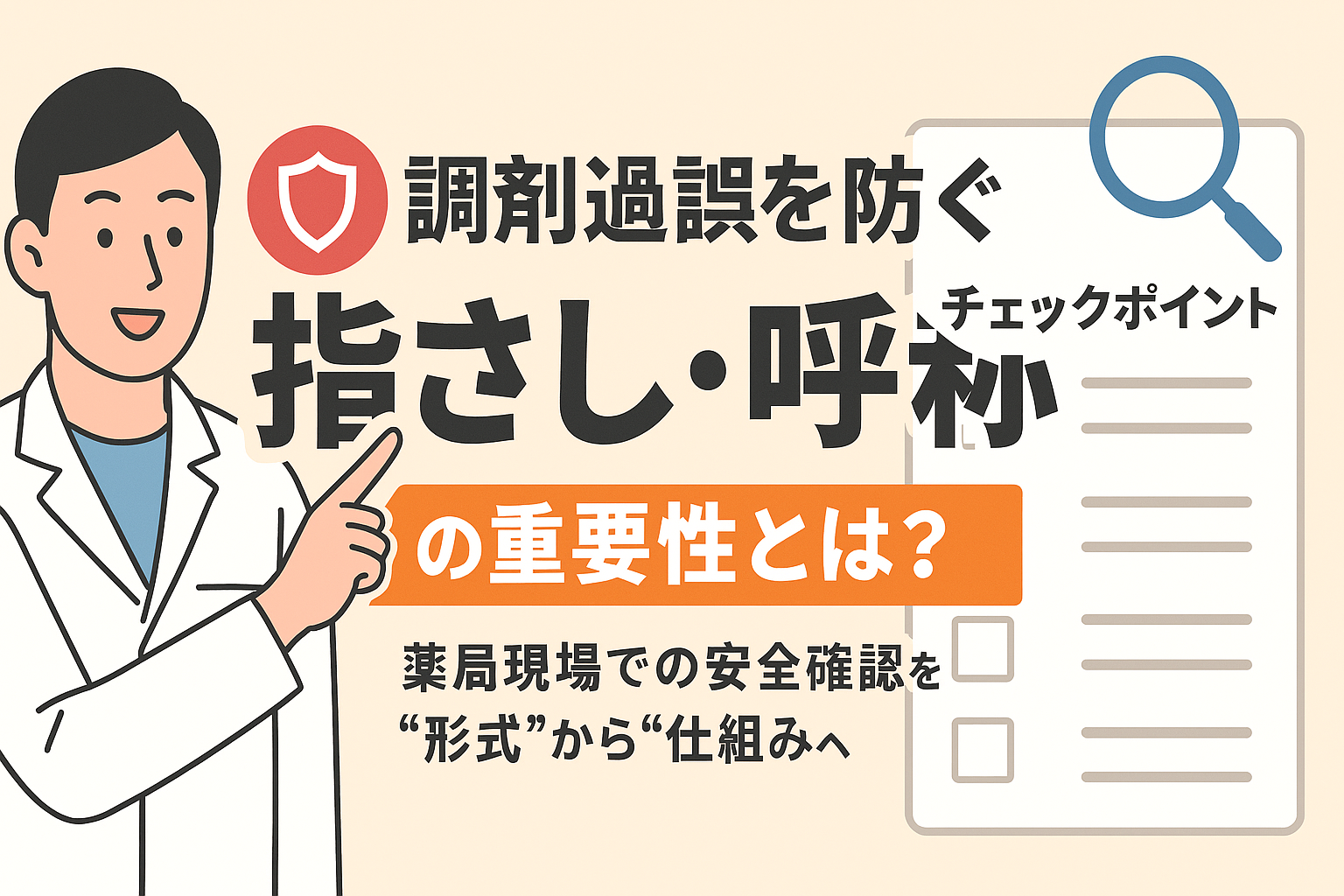
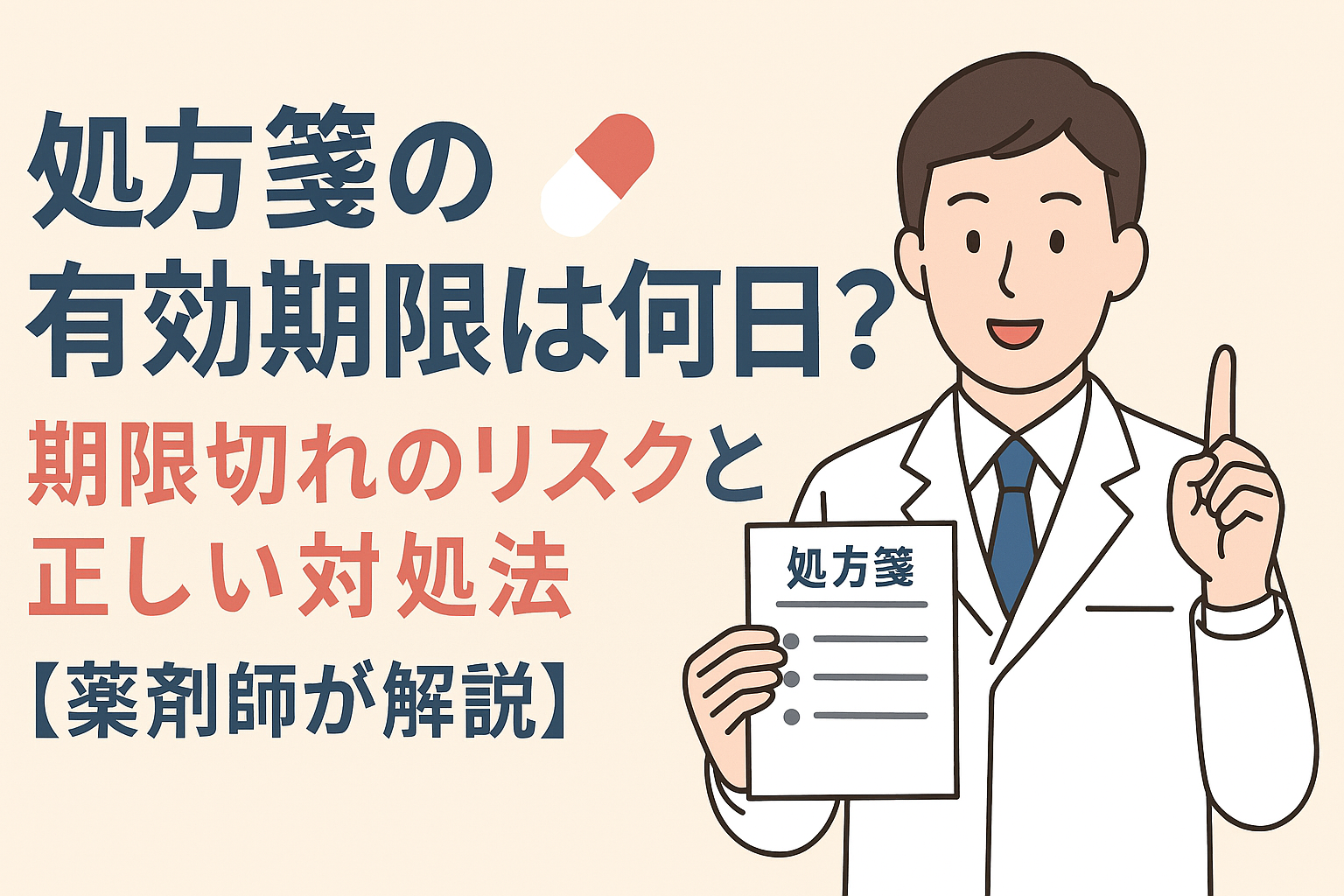
コメント