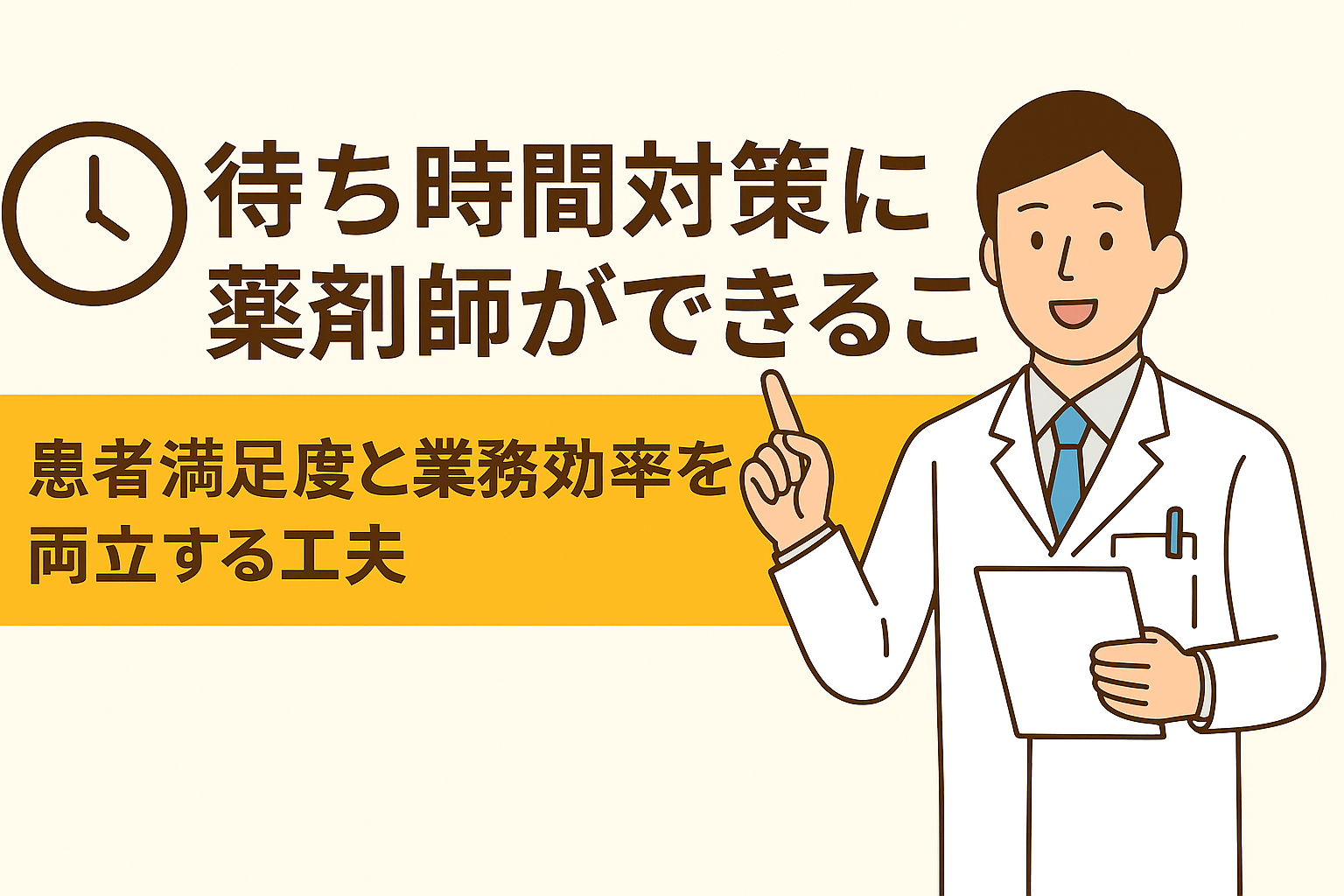🕒待ち時間対策に薬剤師ができること
患者満足度と業務効率を両立する現場の工夫
「薬が出るまで、どれくらいかかりますか?」
薬局で働く薬剤師なら、一度は患者さんから聞かれたことがあるはず。待ち時間は、患者の不安や不満につながりやすいポイントです。
しかし、薬剤師のちょっとした工夫で、待ち時間の印象は大きく変わります。この記事では、薬剤師が現場でできる待ち時間対策を、実践例とともに紹介します。
🧭なぜ待ち時間が問題になるのか?
- 患者の不安や不満につながる
- 高齢者や体調不良の方にとっては身体的負担になる
- 混雑時のクレームや問い合わせが増える
- 薬局の印象や信頼感に影響する
待ち時間そのものよりも、「何も説明がない」「何をしているか分からない」ことが不満の原因になるケースが多いのです。
💡薬剤師ができる待ち時間対策
① 状況説明をこまめに行う
- 「現在○○の確認中です」「あと○分ほどでお渡しできます」など、進捗を伝えるだけで安心感が生まれます。
- 疑義照会や一包化など時間がかかる処方では、説明の有無が印象を左右します。
② 服薬指導の順番を工夫する
- 複雑な処方の患者には、先に説明だけ済ませておくことで、待ち時間の体感を短くできます。
- 「先に説明だけしておきますね」と声をかけるだけでも、患者の不安は軽減されます。
③ 待ち時間中の情報提供
- 健康情報のパンフレットや季節の感染症対策など、待ち時間に読める資料を設置。
- 掲示物やモニターで「薬局の取り組み」や「薬の豆知識」を紹介するのも効果的です。
④ 処方内容の事前確認・予測
- 受付時に「この薬は在庫確認が必要です」「一包化に時間がかかります」と伝えることで、患者の心構えができます。
- 施設処方や定期処方では、事前に内容を予測して準備しておくとスムーズです。
⑤ チーム内連携の強化
- 調剤・監査・投薬の役割分担を明確にし、流れを止めない工夫が重要です。
- 「誰がどこまで終えているか」が見えるようにすることで、無駄な待機時間を減らせます。
🛠現場での工夫事例
- 待ち時間が長くなる処方には、受付時に「目安時間カード」を渡して説明
- 一包化や麻薬処方など、時間がかかる処方には「優先確認フロー」を設けて対応
- 待合スペースに「薬局の裏側紹介」や「薬剤師の仕事紹介」などの掲示物を設置し、理解促進と信頼感向上を図る
🎯まとめ:待ち時間は「対応力」で変えられる
待ち時間をゼロにすることは難しくても、「待っている間の不安」を減らすことはできます。薬剤師が一言声をかけるだけで、患者の印象は大きく変わります。
待ち時間対策は、薬剤師のコミュニケーション力と現場改善力が活きる領域。「薬が出るまでの時間」ではなく、「薬局で過ごす時間」を価値あるものに変えていきましょう。