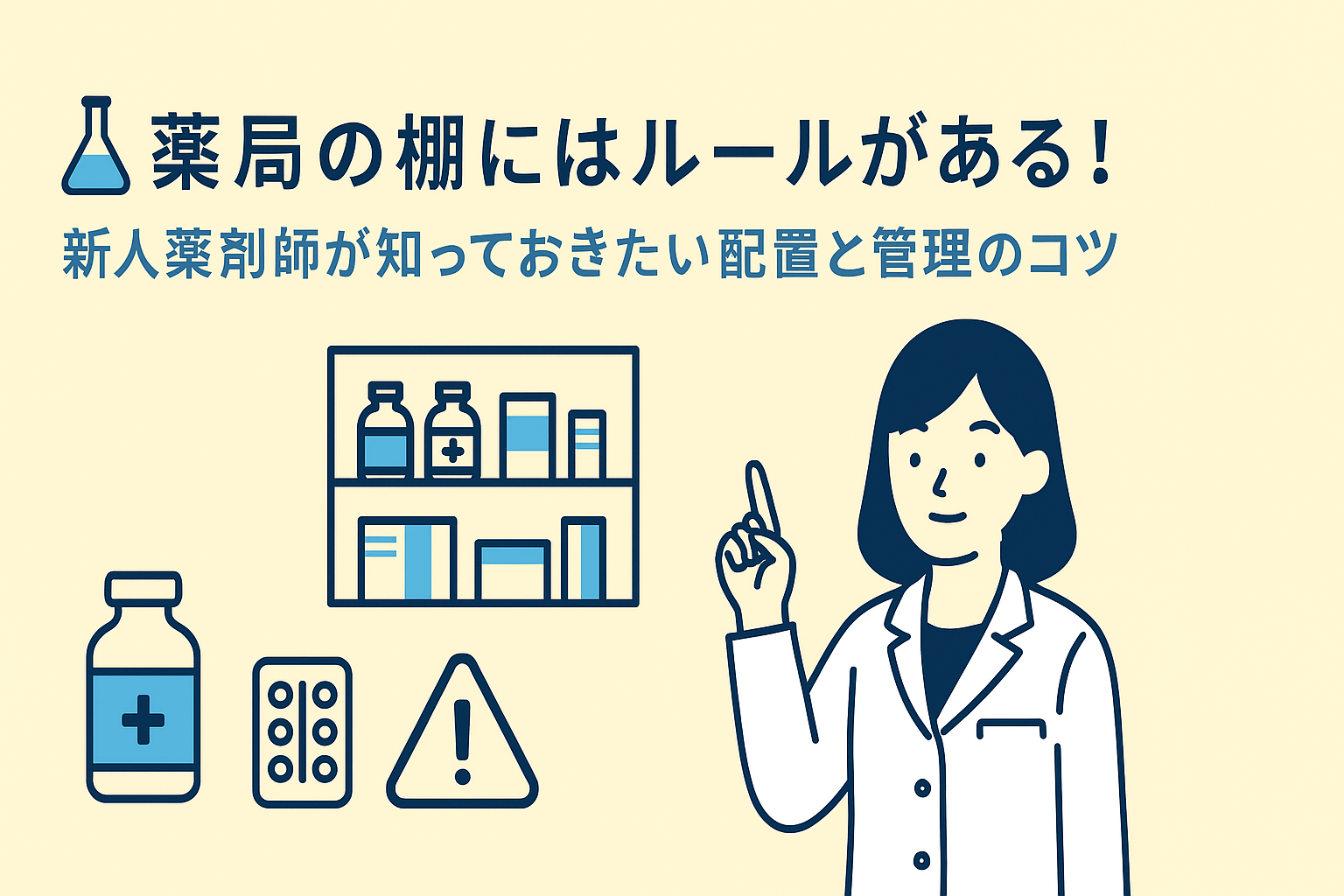🧪薬局の棚にはルールがある!
新人薬剤師が知っておきたい配置と管理のコツ
薬局に配属されたばかりの新人薬剤師が最初に戸惑うのが、「棚の並び方」。薬の配置には明確なマニュアルがあるわけではないのに、先輩たちは迷いなく薬を取り出し、補充し、説明している…。その秘密は「棚ルール」にあります。
このブログでは、薬局でよく使われる棚ルールの基本と、新人薬剤師が現場でスムーズに動けるためのコツを、具体的な事例を交えて紹介します。
🗂棚ルールとは?
棚ルールとは、薬局内で医薬品を配置・管理する際の“現場独自のルール”のこと。マニュアル化されていないことも多く、経験や慣習に基づいて運用されています。
- 誤投薬の防止
- 業務効率の向上
- 教育・引き継ぎのしやすさ
棚の並び方ひとつで、患者の安全も、薬剤師の動きやすさも大きく変わります。
📌棚ルールの具体例とその背景
① 同効薬は並べて配置する
例:ARB系降圧薬(イルベサルタン、ロサルタン、バルサルタンなど)
- 同じ薬効を持つ薬剤を一列に並べることで、比較・説明がしやすくなります。
- 患者に「どの薬を使っているか」「変更の可能性」などを説明する際に便利です。
- 用量や剤形が異なる場合はラベルで明示し、誤投薬を防止します。
② 先発品とジェネリックは隣に配置する
例:アムロジン、ノルバスクとそのジェネリック医薬品(アムロジピン錠など)
- 患者への選択肢提示や薬剤師間の確認がスムーズになります。
- 外箱の色や形状が似ている場合は、ラベルやPOPで区別を強調する工夫が必要です。
③ ハイリスク薬は目立つ位置に配置する
例:抗がん剤(レジメン薬)、抗てんかん薬(ラモトリギン、バルプロ酸など)
- 誤投薬や取り違えが重大な影響を及ぼす薬剤は、棚の最上段や専用ゾーンに配置。
- 赤や黄色のラベル、注意喚起POPを併用し、視認性と緊張感を高めます。
- 一部施設では「ハイリスク薬棚」として独立管理しているケースもあります。
④ 使用頻度順に並べる
例:解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン、ロキソプロフェン)を手前に、漢方薬を奥に
- 処方頻度が高い薬剤は取り出しやすい位置に配置することで、ピッキング効率が向上します。
- 頻度が低くても注意が必要な薬(ワルファリン、メトトレキサートなど)は、視認性を優先して配置します。
⑤ 薬効別にゾーニングする
例:棚A=循環器系、棚B=糖尿病薬、棚C=消化器系薬
- 教育や検索のしやすさを重視した配置。新人薬剤師が薬効分類を学ぶ際にも有効です。
- 複数の薬効を持つ薬(SGLT2阻害薬など)は、どのゾーンに置くか施設ごとに判断が分かれるため、ルールの明示が重要です。
🧠新人薬剤師が気をつけたいポイント
- 配置変更は必ず報告・記録
- 似た名前・形状の薬は離して配置(ヒューマンエラー防止)
- 「この棚のルールはありますか?」と先輩に確認する習慣を
- ラベルや分類が分かりづらい場合は、改善提案も歓迎されることが多い
棚ルールは“守るもの”であると同時に、“育てていくもの”でもあります。疑問を持つことは、改善の第一歩です。
🛠現場での工夫と改善事例
薬局の棚ルールは、単なる並び順ではなく「安全性」と「業務効率」を支える重要な仕組みです。現場での混乱や誤投薬リスクを減らすために、棚の視認性やルールの共有方法を見直し、いくつかの改善を行ってきました。
薬効分類ごとに色分けしたラベルを導入したり、棚の配置図を作成して新人教育に活用したり、ルールの背景や注意点を文章化して共有したりと、現場の声を反映しながら工夫を重ねてきました。
また、こうした取り組みを情報発信することで、他施設の薬剤師との情報交換が生まれ、棚ルールの改善サイクルが加速するという副次的な効果も得られました。
結果として、新人薬剤師が棚の構造を短期間で理解できるようになり、配置変更時の混乱も減少。現場全体の安全性と教育効率が向上しました。
🧭まとめ:棚ルールは“安全”と“効率”の土台
薬局の棚は、ただ薬を並べる場所ではありません。そこには、患者の安全を守るための工夫と、薬剤師の動きやすさを支える知恵が詰まっています。
新人薬剤師にとって棚ルールは、現場に馴染むための第一歩。「なぜこの並びなのか?」という視点を持つことで、より深い理解と改善につながります。
棚ルールを知ることは、薬剤師としての“現場力”を高めることでもあるのです。