🛡️ 調剤過誤を防ぐ「指さし・呼称」の重要性とは?
薬局現場での安全確認を“形式”から“仕組み”へ
🔍 はじめに:調剤過誤は誰にでも起こり得る
薬局業務において、調剤過誤は患者の健康に直結する重大なリスクです。処方内容の読み違い、薬剤の取り違え、ラベルの貼り間違いなど、些細なミスが大きな事故につながる可能性があります。
そのようなリスクを最小限に抑えるために導入されているのが「指さし・呼称」という確認手法です。鉄道や製造業などの安全管理で広く使われており、医療現場でもその有効性が実証されています。
🧠 指さし・呼称とは何か
指さし・呼称(指差喚呼)とは、確認対象を指さしながら、声に出して名称や状態を呼称することで、視覚・聴覚・運動感覚を同時に使って注意力を高める確認手法です。
この方法は、単なる「確認したつもり」を防ぎ、脳の複数の感覚を刺激することで、認知ミスや思い込みによるエラーを減らす効果があります。
たとえば、薬剤を取り出す際に「ロキソニン錠60mg、1日3回、7日分」と声に出しながら、薬剤を指さして確認することで、目と耳と手の動きが連動し、注意力が格段に高まります。
📊 実証された効果:エラー発生率が1/3〜1/9に減少
指さし・呼称の効果は、複数の研究で実証されています。看護師を対象とした実験では、内服薬の照合作業において以下の結果が得られました:
- 指さし・呼称あり:平均エラー数 0.5回
- 指さし・呼称なし:平均エラー数 1.4回
薬の配布場面では:
- 指さし・呼称あり:0.1回
- 指さし・呼称なし:0.9回
このように、指さし・呼称を導入することで、エラー発生率が最大で約1/9に減少することが確認されています。
🧪 現場での実践例
💊 処方鑑査の場面
1人目の薬剤師が処方内容を確認し、薬剤を選定。2人目の薬剤師が薬剤と処方内容を照合し、薬袋やラベルの記載を確認します。
この際、「声出し確認」をルール化することで、曖昧な確認を防ぎます。
例:「〇〇さん、ロキソニン錠60mg、1日3回、7日分。薬袋の記載も確認しました。」
📝 薬歴記載の場面
服薬指導後、薬歴を記載した薬剤師とは別の薬剤師が「要点のみ」を確認します。服薬指導の内容、残薬の有無、副作用の確認などが記載されているかをチェックします。
⚠️ よくある課題と改善策
| ❌ よくある課題 | ✅ 改善ポイント |
|---|---|
| 忙しくて省略されがち | 業務フローに組み込み、必須工程として定着させる |
| 恥ずかしさ・照れがある | チーム全体で実施し、文化として根付かせる |
| 定着しない | 効果を体感できる研修やロールプレイを導入する |
| 意識が薄い | エラー事例を共有し、危機感と目的を明確にする |
| 形式だけになっている | チェックリスト化し、記録に残す仕組みを導入する |
📑 薬局で使える指さし・呼称チェックポイント
- □ 処方内容と薬剤名を指さしながら声に出して確認
- □ 規格・数量・剤形を指さしながら復唱
- □ 薬袋・ラベルの記載内容を指さして読み上げ
- □ 患者氏名をフルネームで呼称し、リストと照合
- □ 疑義照会の記録内容を声に出して確認
- □ チェック者の記録を残す(電子薬歴・紙台帳)
🧭 まとめ:指さし・呼称は「安全文化」の第一歩
指さし・呼称は、単なる確認動作ではありません。それは、薬局全体で患者の安全を守るための文化であり、仕組みです。
「見たつもり」「言ったつもり」を防ぐことで、調剤過誤のリスクを大幅に減らすことができます。忙しい現場だからこそ、確認の質を高める工夫が必要です。
薬局での指さし・呼称、今こそ見直してみませんか?小さな確認の積み重ねが、大きな安心につながります。
📝 筆者について
本記事は、薬剤師として現場経験を持つ筆者が、医療安全の実践と教育活動を通じて得た知見をもとに執筆しています。
調剤過誤の防止は、薬剤師の使命であり、患者の安心につながる最も重要な業務のひとつです。
現場での再現性と実用性を重視し、読者の皆さまがすぐに活用できる情報を提供することを心がけています。
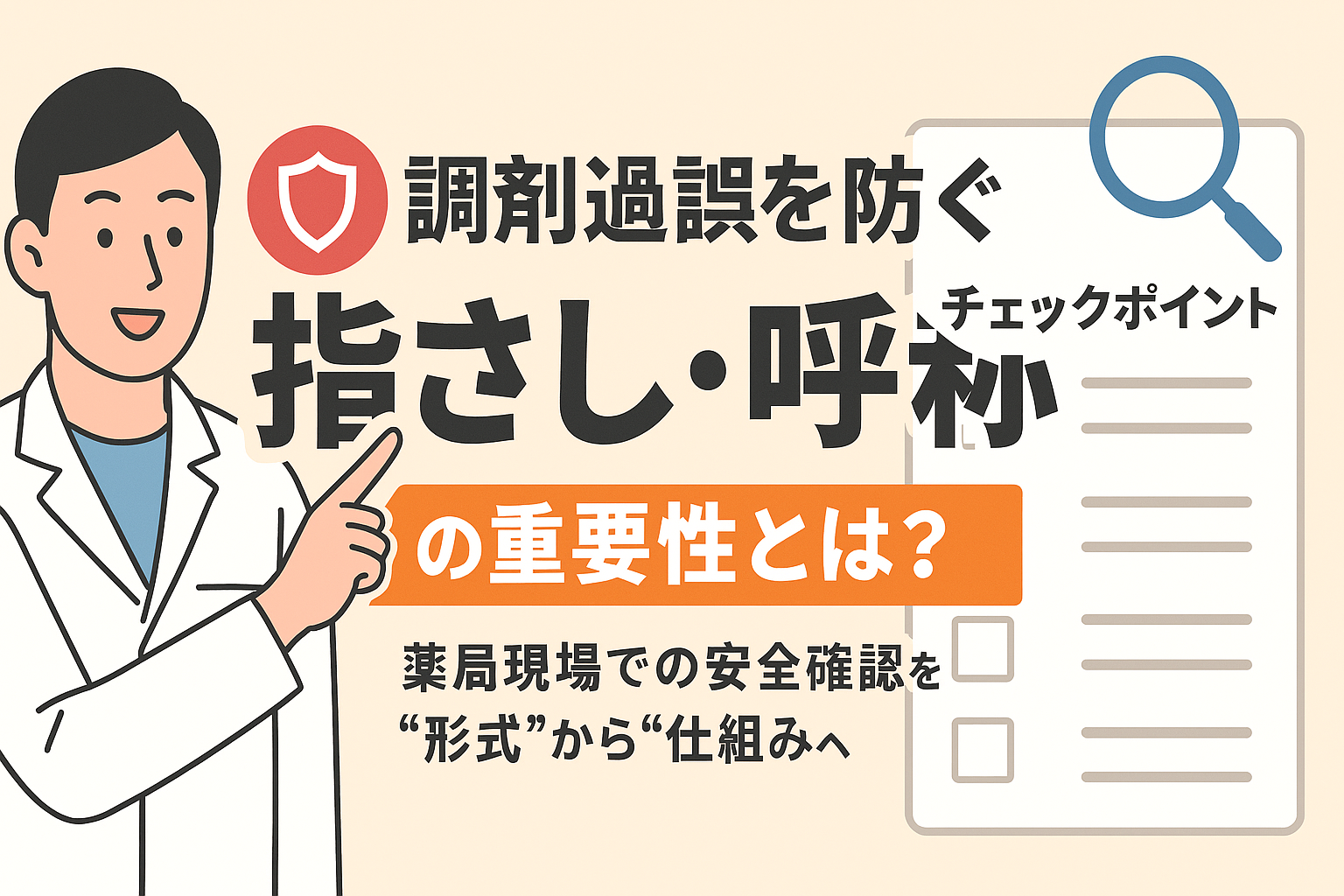
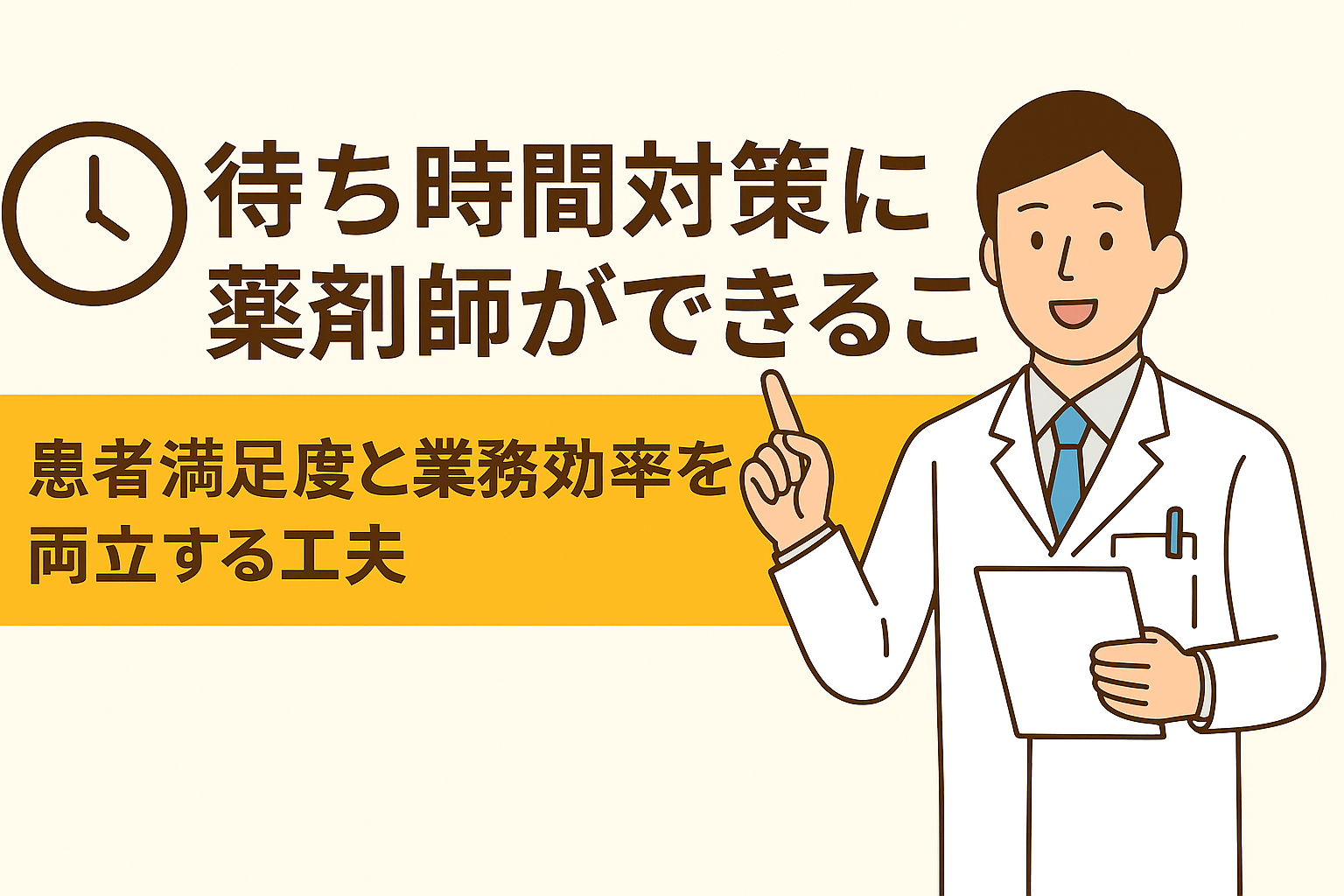
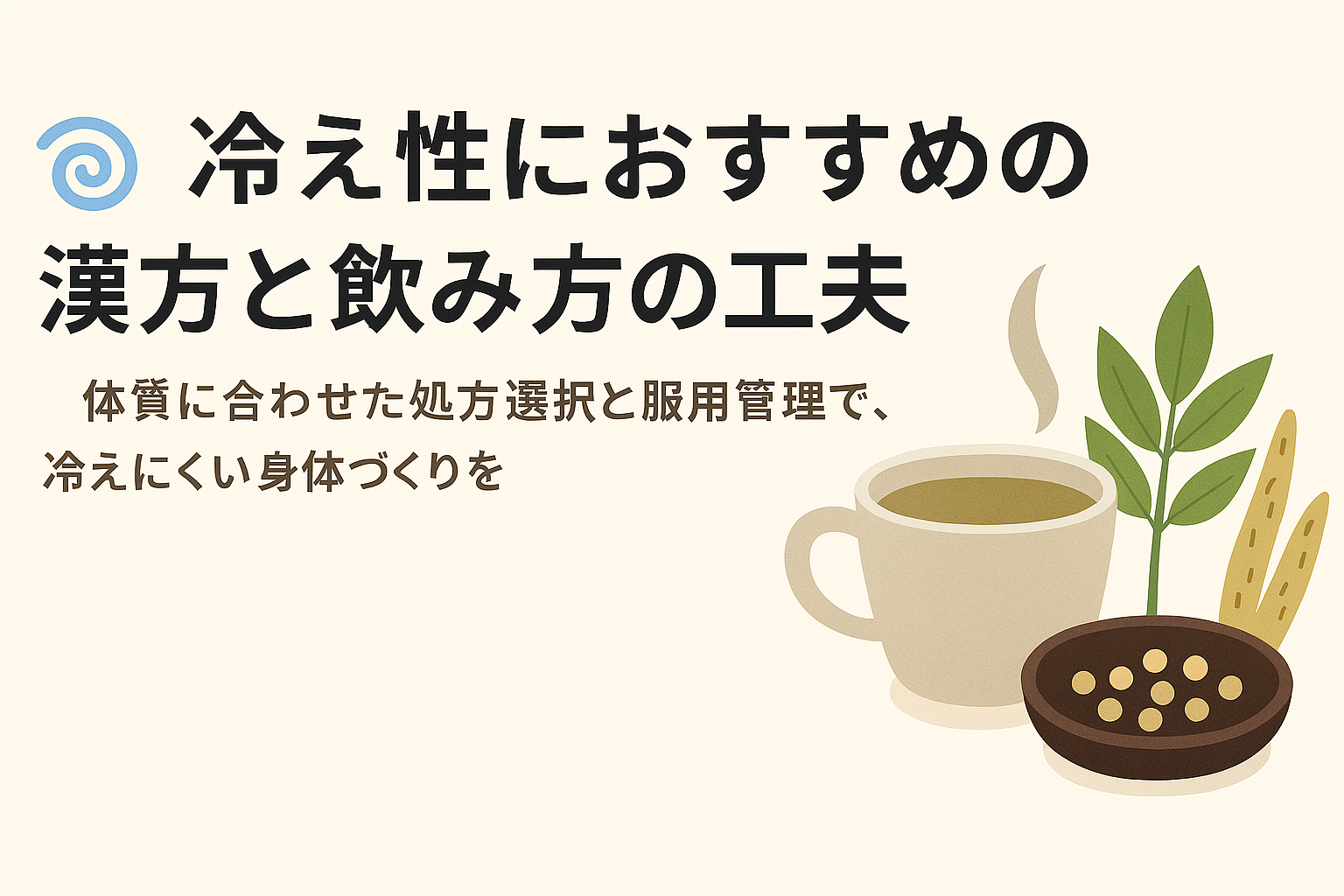
コメント