❄️冷え性×漢方|証から読み解く体質別処方
✅この記事でわかること
- 漢方における「証」とは何か
- 冷え性のタイプ分類と原因
- 証に基づく漢方薬の選び方
- 冷え性改善のための生活習慣と食事
- 漢方認定試験にも役立つ知識
🧠漢方の「証」とは?|体質診断の核心
漢方医学では、病名よりも「証(しょう)」を重視します。証とは、患者の体質・症状・気血水のバランス・生活背景などを総合的に判断した診断の型です。
| 証の分類 | 特徴 |
|---|---|
| 寒証 | 冷え、顔色が白い、温かいものを好む |
| 熱証 | のぼせ、口渇、顔色が赤い |
| 虚証 | 体力低下、疲れやすい、声が小さい |
| 実証 | 体力あり、症状が強く出る、便秘など |
🔍冷え性タイプ別:証と処方の完全ガイド
🔥熱源不足タイプ(寒証・虚証)
| 証 | 主な症状 | 処方例 |
|---|---|---|
| 気虚 | 疲れやすい、息切れ、食欲不振 | 補中益気湯、人参湯、黄耆など |
| 血虚 | 顔色が青白い、めまい、月経不順 | 当帰芍薬散、四物湯、地黄など |
| 陽虚 | 手足の冷え、寒がり、頻尿 | 八味地黄丸、真武湯、附子・乾姜など |
🔄循環不足タイプ(気滞・瘀血・水滞)
| 証 | 主な症状 | 処方例 |
|---|---|---|
| 気滞 | イライラ、胸のつかえ、便秘 | 加味逍遙散、半夏厚朴湯、柴胡など |
| 瘀血 | くすみ、肩こり、冷えのぼせ | 桂枝茯苓丸、桃核承気湯、紅花など |
| 水滞 | むくみ、頭重感、関節痛 | 五苓散、防己黄耆湯、茯苓・沢瀉など |
🍽️冷え性改善の生活習慣と食事|体質別・実践的アプローチ
🔥温める食材
| 食材 | 特徴と作用 | 活用例 |
|---|---|---|
| 生姜 | 発汗・血行促進・胃腸温め | 生姜湯、炒め物、味噌汁 |
| ねぎ | 解表・温中・風邪予防 | 鍋物、薬味、味噌汁 |
| にんにく | 血流改善・抗菌・温陽 | 炒め物、スープ、漬物 |
| シナモン | 血管拡張・冷えのぼせにも有効 | ハーブティー、焼き菓子 |
| 羊肉 | 補陽・造血・体力回復 | シチュー、鍋、スープ |
| 黒豆 | 補腎・利水・血行促進 | 黒豆煮、炊き込みご飯、スープ |
🚫避けたい習慣
- 冷たい飲食物の摂取(胃腸を冷やし、気血生成力を低下)
- 湯船に浸からない生活(深部体温が上がらず、末端冷えが改善しにくい)
- ストレス過多・運動不足(気滞や筋肉量低下による冷え悪化)
✅おすすめ習慣
- 三首(首・手首・足首)を温める(血管が表面に近く、体温調節に影響大)
- 軽い運動(ウォーキング・ストレッチ)で筋肉による熱産生を促進
- 睡眠と休息の確保(自律神経を整え、血流改善)
📚漢方認定試験対策にも使える知識
1. 証の分類と特徴は頻出項目
| 証の分類 | 特徴 | 試験ポイント |
|---|---|---|
| 寒証 | 冷え、顔色が白い、温かいものを好む | 冷え性・虚寒証との関連性 |
| 熱証 | のぼせ、口渇、顔色が赤い | 実熱証との違いを明確に |
| 虚証 | 体力低下、疲れやすい、声が小さい | 補益薬の適応判断 |
| 実証 | 体力あり、症状が強く出る、便秘など | 瀉下薬・理気薬の選定根拠 |
2. 処方と生薬の組み合わせを暗記
| 処方名 | 主な構成生薬 | 適応証 |
|---|---|---|
| 補中益気湯 | 人参・黄耆・白朮・当帰・陳皮・柴胡・升麻・甘草・生姜・大棗 | 気虚・寒証 |
| 当帰芍薬散 | 当帰・芍薬・川芎・茯苓・白朮・沢瀉 | 血虚・水滞 |
| 八味地黄丸 | 地黄・山茱萸・山薬・沢瀉・茯苓・牡丹皮・桂皮・附子 | 陽虚・寒証 |
| 桂枝茯苓丸 | 桂皮・茯苓・牡丹皮・桃仁・芍薬 | 瘀血・実証 |
3. 冷え性は「虚寒証」「実寒証」の違いを明確に
| 項目 | 虚寒証 | 実寒証 |
|---|---|---|
| 原因 | 体力・陽気の不足 | 外寒の侵入・寒邪の停滞 |
| 症状 | 手足の冷え、疲労感、顔色が白い | 急な冷え、腹痛、下痢、舌苔白厚 |
| 舌診 | 淡白、湿潤、薄い苔 | 白苔厚く、滑りやすい |
| 脈診 | 沈細、弱い | 沈緊、有力 |
| 処方例 | 補中益気湯、八味地黄丸、真武湯 | 大黄附子湯、五積散、小青竜湯 |
4. 気血水理論と五臓六腑の関係性を理解
| 五臓 | 関連する気血水 | 主な役割 | 冷え性との関係 |
|---|---|---|---|
| 肝 | 血・気 | 血の貯蔵・気の疏泄 | 肝血虚→月経不順・末端冷え |
| 心 | 血・気 | 血脈の運行・精神活動 | 心血虚→不眠・冷えのぼせ |
| 脾 | 気・水 | 飲食物の消化吸収・気血の生成 | 脾気虚→エネルギー不足・冷え |
| 肺 | 気・水 | 呼吸・水分代謝・免疫 | 肺気虚→体表の防衛力低下・寒がり |
| 腎 | 気・水・精 | 生命力の根源・水分代謝 | 腎陽虚→下半身の冷え・頻尿・疲労感 |
📝まとめ|冷え性は「証」で読み解く
冷え性は単なる「寒さ」ではなく、体質の乱れのサインです。漢方では「証」に基づいて、個々の体質や症状に合わせた処方を選び、根本からの改善を目指します。
- 証の理解は、漢方認定試験対策にも臨床応用にも不可欠
- 冷え性は「虚寒証」「実寒証」「気滞」「瘀血」「水滞」など多様な背景を持つ
- 食事・生活習慣の見直しも、漢方治療の効果を高める重要な要素
※冷え性関連の記事→冷え性改善に効く漢方と飲み方の工夫 | 薬剤師ブログ&相談室
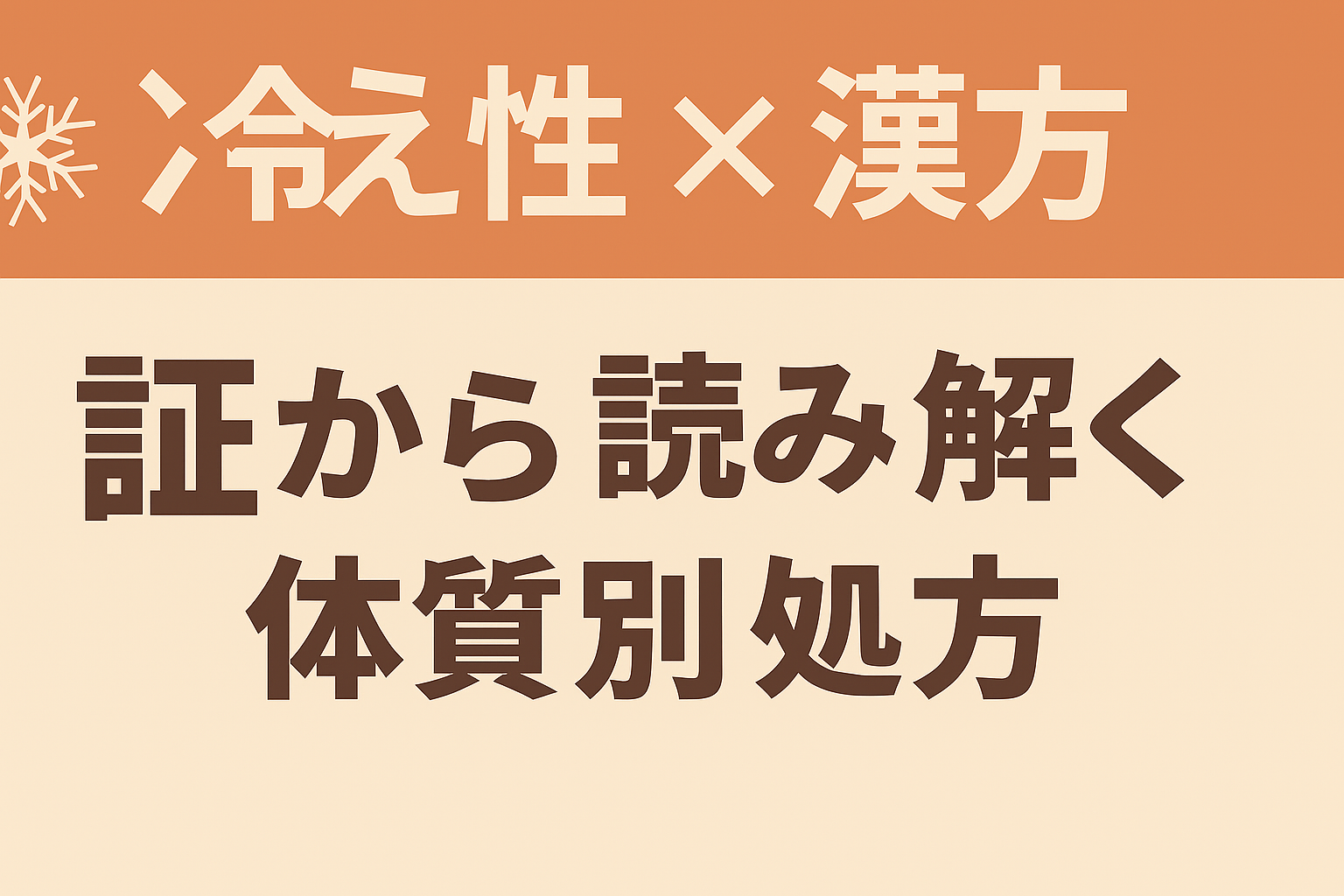
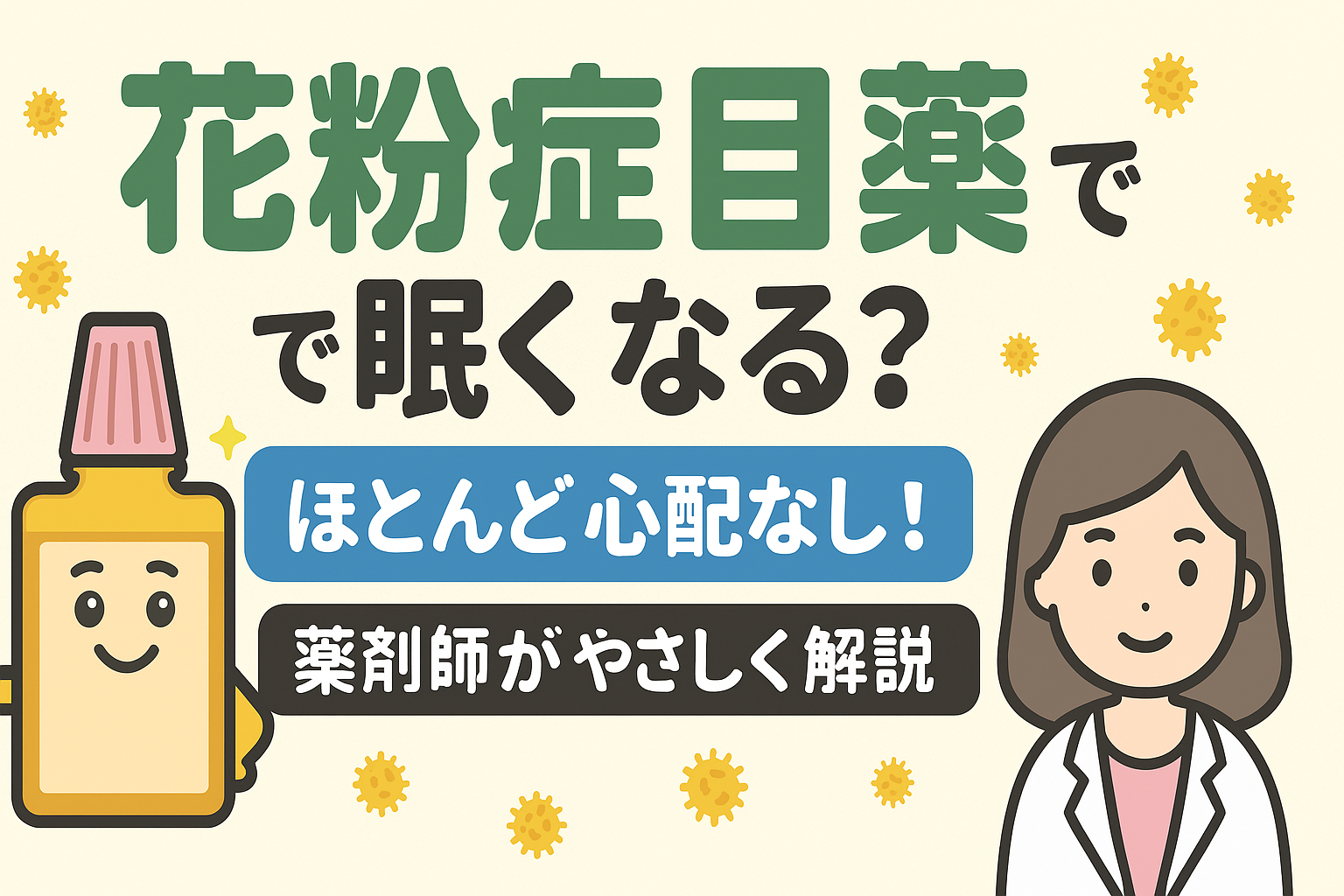
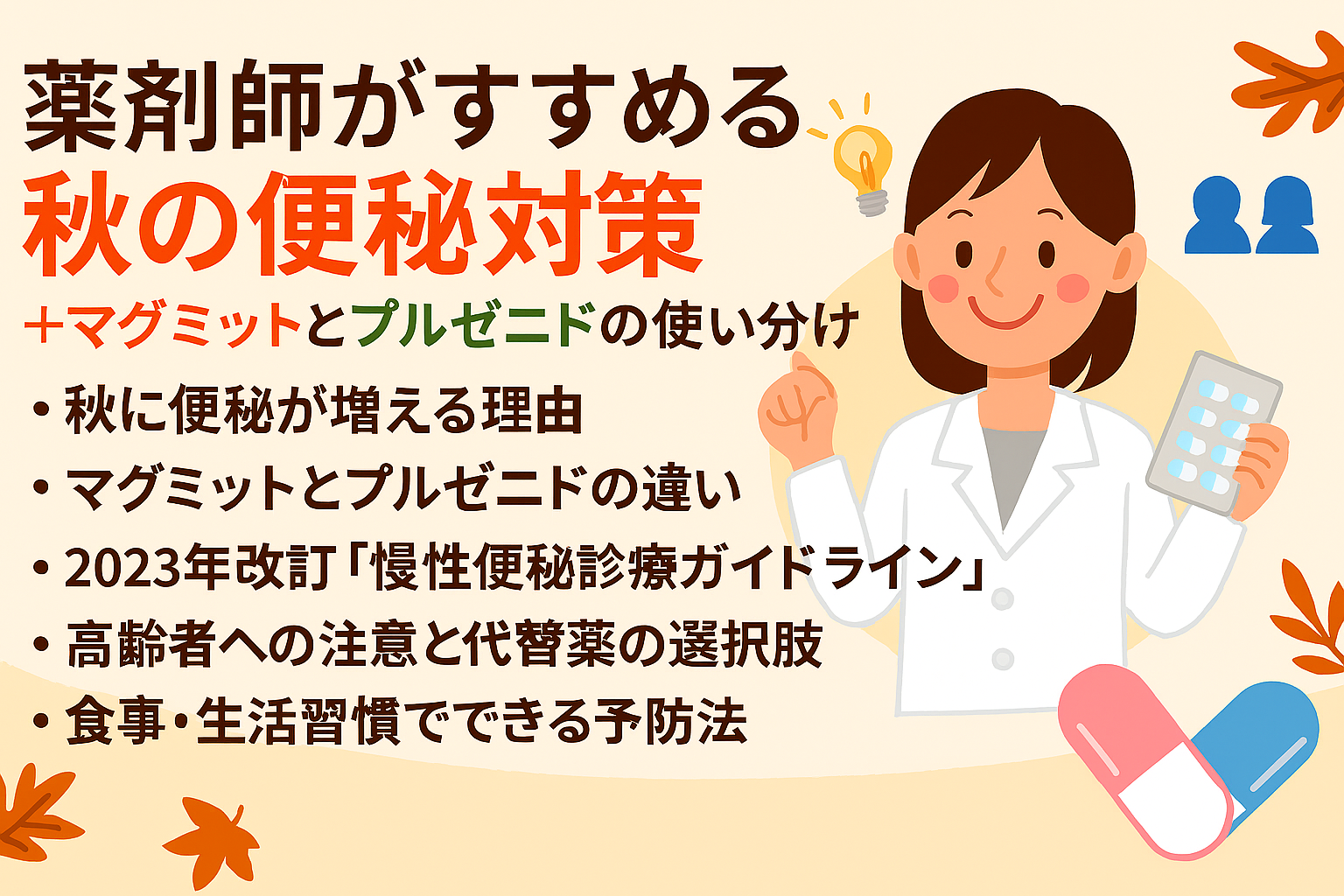
コメント